無垢スタイルのリノベリフォームの吉田です。
今回は「50年前の床下の考え方」について、
古民家の床下の特徴などに触れながらお話したいと思います。

「古民家」とはどんな住まいを指すの?
最近、ちょっとしたブームの「古民家」。
定義をすると、今から50年ほど前の住まいにあたります。
古民家というと「築100年」とか「江戸時代」とかを想像しがちですが、実はそんな事はないのですね。
住宅が大量供給時代に入る昭和40年代以前は同じ様な工法で建てられており、
築50年程度の家は「古民家」に分類されるものが数多く存在します。(諸説あります)
古民家の床下ってどんなもの?
先日、調査した築50年前後の民家の床下写真です。

床板を支える木材全てが無垢材で、ほぼ丸太の状態で使用されている事がわかります。
木と木の間には隙間も多いですね。
奥に見える縦に幾重にも走る白い線は外側の光です。
また、1階床と地面との隙間が広く、この民家で70センチメートルほどありました。
現代の住宅の床下
こちらは築30年程度の戸建て住宅の床下で、大量供給時代の建物です。

木材は製材(寸法を均一に加工した)されたものを使用し、
職人さんが工事しやすく効率化が図られてきています。
コンクリートの基礎も普及してきています。
奥が暗いのはコンクリートの基礎に覆われているためで、
2m〜3mに1箇所程度通気用の穴を開ける事が一般的でした。
地面と1階床の隙間は約45センチメートルです。
この作り方は今でも普及している工法ですが、最近一般化されているのは
- ・耐震性を上げるコンクリート基礎
- ・断熱性を上げるための断熱施工
- ・湿気対策
- ・シロアリ対策
を施したものです。
古民家の床下と現代の床下の違い。それぞれのメリット・デメリットとは?
50年前の床下は、湿気を逃がすための工夫がなされており、
木材を健全な状態に保つための工夫がなされています。
- 【メリット】
- →長持ちします。
- 【デメリット】
- →冬、直接隙間風が室内に入り、底冷えします。
- →耐震性に不安が残ります。
一方、現代の床下は、湿気による様々な害に対策を施した工法となっています。
- 【メリット】
- →断熱性が向上した
- →耐震性が向上した
- 【デメリット】
- →しっかりとした施工をしないと不具合が生じる (シロアリ、断熱性・耐震性低下など)
50年前の古民家の床下は風通しと長持ちに特化した「シンプル構造」で、
現代の住宅の床下は性能を向上させた分、
発生する障害に対策を施した「複雑な構造」ということがわかります。
築20〜40年前後の床下は要注意
50年前と比べて変化しているのは工法だけではなく、
建てる場所も材料も、職人も住む人の考え方も大きく変わっています。
ひとつひとつに目を向けなければ、現代の性能は守られないというのが現状です。
注意したいのは、現在の工法が確立される間に建てられた建物、
築20年〜築40年前後の床下の状態です。
風通しが悪ければ、製材された木材には湿気が溜まり弱くなってしまったり、
隙間風が壁の中を登り結露、カビの発生原因になったりという状態が考えられます。
「住まいの問題解決業」として、無垢スタイルは有資格者による無料点検を実施中!

私どもリフォームに携わるものはそれらを改善する方法を提案していくことが大きな役割と考えております。
無垢スタイルは、有資格者による無料の床下点検を行っています。
シロアリ被害や湿気、耐震など、しっかり確認し、写真付きで診断結果を詳しくお伝えしています。
現在古民家にお住まいの方や、
これから古民家のリフォーム・リノベーションをご検討されている方も大歓迎です。
家の建築施工を総合的に行っている無垢スタイルだからこそ、
建物の構造を熟知した経験豊富なスタッフが最善のご提案をいたします。
表向きだけのリフォームに踏み切る前に、ぜひ一度無垢スタイルにご相談ください。

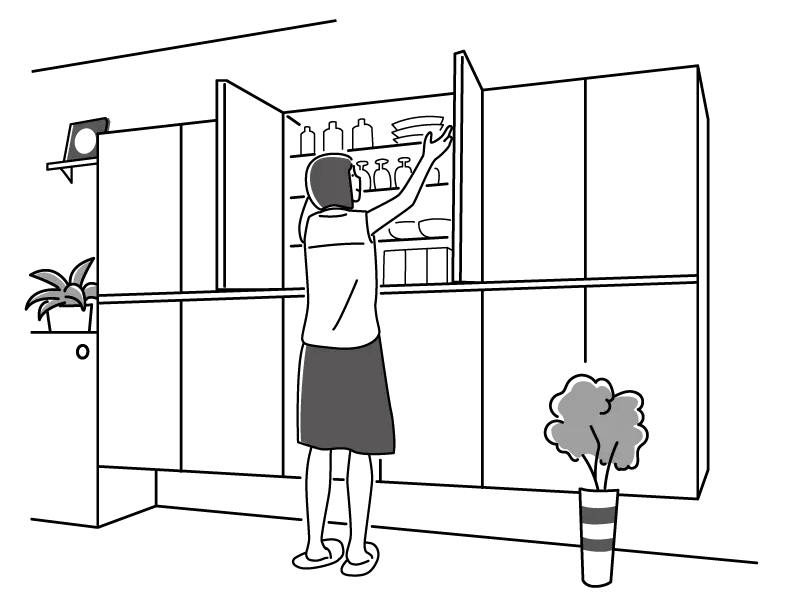
無垢スタイルのモデルハウス・ショールームで、見て・触って・体感できます!
無垢スタイルでは便利な収納アイデアを体感できるモデルハウス・ショールームをご用意しています。
収納リフォーム、またはリノベーションをご検討の方は是非モデルハウス・ショールームにお気軽にお越しくださいませ!